
【Hoopus.イベントレポート 後編】気候変動・サステナビリティに関するキャリア座談会 実践者のキャリアビジョンやセクターごとの違いは?
Hoopus.は、サステナビリティに携わるメンバーの相互学習型コミュティ、サステナブルコミュニティとの共催で、セクターを超えて気候変動に関わるキャリアパスの可能性を考える、オンラインのトークイベントを開催しました。
イベントレポート後編では、サステナブルコミュニティ代表理事の山路 祐一(やまじ・ゆういち)さんにお話しいただいた、サステナビリティのプレイヤーの集まりであるサステナブルコミュニティ立ち上げの経緯や、ご自身のキャリアについて、そして、山路さん・平神さん・久保川さん3人のキャリア座談会の模様をレポートします。
750人のサステナビリティ実践者が集まるコミュニティ
サステナブルコミュニティの山路祐一さんからは、コミュニティの立ち上げの経緯や、サスコミュが発表している、メンバー14人のキャリアに焦点を当てた「ESGキャリアガイドブック」についてお話しいただきました。
サステナブルコミュニティ 山路祐一さんのキャリア

山路祐一/一般社団法人サステナブルコミュニティ代表理事 大学卒業後、印刷会社とIR支援会社にて統合報告書やサステナビリティレポートなど非財務情報開示支援業務に11年従事。その後、製造業でのサステナビリティ推進業務を約5年経験し、現在もサービス業にてサステナビリティ推進業務を担当。2021年5月に任意団体サステナブルコミュニティを設立した後、2023年5月に一般社団法人サステナブルコミュニティとして法人化し代表理事に就任。
山路さん:キャリアの原点になっているのは、大学時代にコンプライアンスや企業不祥事の原因などを学ぶなかで、CSRという言葉を知ったことです。大学時代に学んだCSRに関する仕事に就きたいと思い、卒業後は、企業の情報開示という領域へ進みました。新卒は専門印刷会社でサステナビリティレポートなどの開示支援、次にIR支援会社に移り統合報告書など投資家向けの情報開示支援、3社目で製造業のCSR推進室に移り、自社のサステナビリティ推進を経験しました。特に3社目では、世界的なカーボンニュートラルの流れを受けて、顧客からのサステナビリティに関する要請への対応や、調査表の回答、国際的な潮流についての情報収集などに従事していました。現在は、サービス業にてサステナビリティ推進の業務を担当しています。
サステナビリティのプレイヤーが集まるコミュニティ
サステナブルコミュニティは、一言でいうとサステナビリティをテーマとしたサークルです。会社を代表するオフィシャルな立場ではなく、いち個人として本音や課題を自由に話せる場として立ち上がり、今では750名を超える人が集まってくれている団体となっています。
サステナブルコミュニティは、本当に偶然立ち上がったコミュニティです。コロナ禍の時期に、リアルな横のつながりがなくなった際に、当時Twitterで呼びかけをして集まってくれた方々と任意団体として立ち上げたことが始まりです。人とのつながりやご縁は、立ち上げ当初から運営の根幹として大事にしていることです。
サステナビリティを仕事にするキャリアのモデルケースを示す「ESGキャリアガイドブック」
サステナブルコミュニティでは、「ESGキャリアガイドブック」を作成して発表しています。このキャリアブックも、私が作ろうといったわけではなく、メンバーの方からこういった情報を整理して発信をしたいというアイデアをいただき、ビジネスのためではなく、コミュニティメンバーの方のための情報として、作るようになったものです。
キャリアガイドブックVol.2を2024年4月に外部公開しました。コミュニティのメンバー14名に、どういった経緯でサステナビリティ担当者になったのか、今のお仕事は何なのか、を中心に一人ひとりインタビューして、サステナビリティを仕事にする上でのキャリアパスを示しながら、いわゆるモデルケースという形で示しています。今後のキャリアを考える際の一つの指針としてご活用いただければありがたいと思っています。
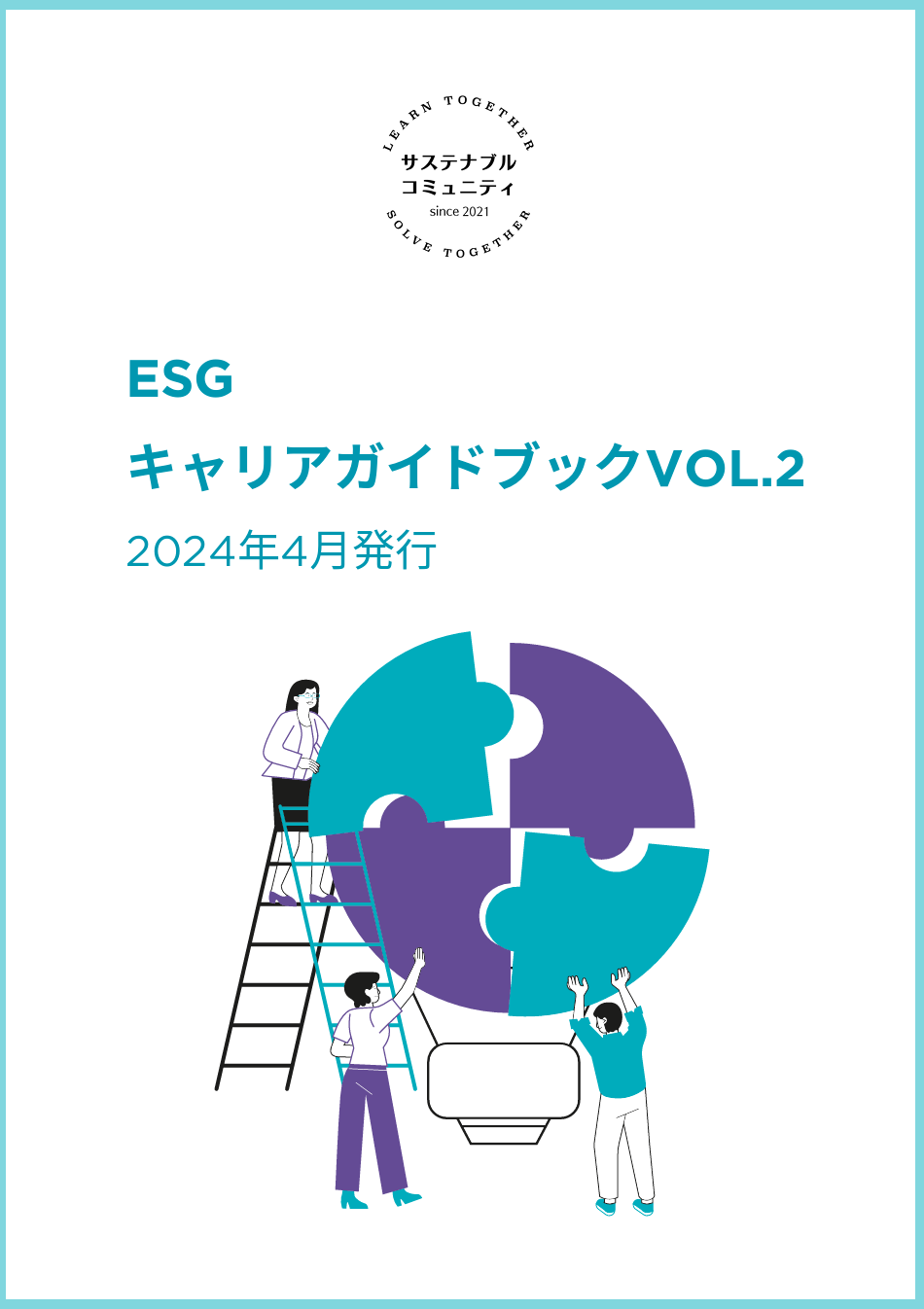
今回のイベントのテーマは、セクターを超えたキャリア形成で、実際に事業会社からNPOに移られた方もコミュニティメンバーの中にいますが、事例としてはまだ揃っていないというのが現状です。だからこそ、このイベントのような、セクターを超えた人財交流の橋渡しをする機会が必要なのではないかと改めて感じています。
サステナビリティ実践者のキャリア座談会
イベント後半では、サステナブルコミュニティの山路さん、自然エネルギー財団の平神さん、Transition Asiaの久保川さんの3人に、キャリア選択についてクロストークをしていただきました。
Q. セクターや業種を超えた転職で、働き方やマインドなどについて、ギャップはありましたか?
平神さん:前職の企業では一人ひとりの役割がきっちり分けられていたのに対して、自然エネルギー財団では気候変動イニシアティブ(JCI)の事務局としてかなりいろんなことを担当していて、一人ひとりが担う役割の幅が広く、刺激がありますね。
働き方については、ここまでやれば自分の仕事が終わる、というものがないので、やろうと思えばいくらでもやりたいことがあり、どこまでも仕事を増やせてしまうという点が難しいです。どこで線引きをして、どの仕事に集中するか選んでいかなくてはいけません。
久保川さん:私の場合は、Transition Asiaが国際的な組織だということもあり、日本的な組織とは全く働き方が異なるというところがあると思います。Transition Asiaの働き方は、とにかく自由です。インターネットがあって、決められたミーティングや予定に合わせさえすれば、世界のどこにいてもいいし、仕事をいつするかも自由です。
そして「シンプルにやろう」という姿勢が見えますね。特に政府機関や公共機関では、会議前に誰かのインプットや合意をとっておくなど、根回しがあったのですが、Transition Asiaに入って最初のうちにそれをやっていたら、鬱陶しがられてしまいました(笑)。「なんで今言うの?あと1時間後にチームミーティングがあるんだから、そこで言えばいいじゃないか」と。一方で、根回しがないので、ミーティング中に突然意見を求められます。その場で、すぐに自分の意見が言えるように常に考えておかなければいけません。
山路さん:私は企業間でも、ビジネスのフィールドによる違いを感じますね。前職では海外売上が70%を占めていたので海外の顧客とのコミュニケーションも多く、海外動向を受け取ったりサステナビリティに関する顧客要請がダイレクトに来たりしていました。顧客との関係構築というビジネスの基本的な文脈で、サステナビリティ対応を進める必要がありました。現在の顧客は、国内中小企業の経営者が中心ですので、外部からの圧力があまりない代わりに、経営者自身が脱炭素の時流をどう見ているのか、脱炭素を成長のテーマの1つとして捉えているかが重要となり、その差を肌で感じています。
Q. ご自身が働くセクターは、気候変動への取り組みにおいてどのような役割や特徴があると思いますか?
久保川さん:営利企業ですと、競合他社がどう動いているか、あるいは自社にメリットがあるかを常に考えなければなりませんが、非営利セクターでは、そうした障壁が少ないです。それが社会のために必要なのであれば、自分たちのノウハウを共有したり、共同研究をしたりできます。
平神さん:私が担当しているJCIとしては、いろいろなステークホルダーを巻き込んで、社
会全体で取り組んでいく仲間を増やしていくという役割があると思っています。JCIは今日本で一番大きな気候変動に関わるプラットフォームですが、企業・自治体・ユース・NGOが全部同じところに集まったネットワークというのはなかなか他にないと思います。例えばセミナーなどのイベントに、大学やユースグループ、NGOなどが登壇し、会場で企業のサステナビリティ担当が普段話す機会がない人の話を聞くというような、さまざまな角度からの情報発信・共有ができています。
あとは、政府への政策提言においても、脱炭素を進めたいという企業を取りまとめて発信できる場は多くないので、大事な取り組みだなと思います。NGOやシンクタンクが声を届けるだけではなくて、企業や自治体などと進めていけるようにすることも重要な役割だと思っています。
山路さん:平神さん・久保川さんのお仕事は、動かない大きな山をなんとかして動かしていこうという、ルールチェンジを目指すマクロな視点でお仕事をされているイメージを持ちます。私が所属している会社では、山を動かす役割というよりは、山が動く中でどこにビジネス機会があるのか、またはどこでリスクを取らなければいけないのかというようなミクロな視点で見ています。それぞれの場所にいるプレイヤーが横でつながることの大事さを感じますし、セクターがつながるというところから、何かが動いていくんじゃないかなと感じますね。
Q. 今後のキャリア形成について考えていることや、悩んでいることがあれば教えてください。
山路さん:今後10年、20年、ビジネスパーソンとしてどこにゴールを置こうかと私も日々模索しているところですが、キャリアビジョンとしては、本業だけに依存せずにいくつか柱を作れるようになりたいと思っています。現在は、仕事としての自分、個人と仕事が若干混じるようなサステナブルコミュニティの代表理事としての自分、そして完全プライベートの自分と、柱が整いつつある状況です。サステナブルコミュニティを通じて、たくさんの仲間がいて語り合えるという環境に、私自身毎日刺激を受けています。
平神さん:私は転職してもうすぐ2年になりますが、非政府アクターの連携業務としてかなり幅広い業務を担当しています。自然エネルギー財団は再エネのシンクタンクですので、専門家や研究者が多いのですが、そこに所属をしているからには、自分も専門的な知識をつけて自分自身の言葉で発信できるようになって、研究者や企業、自治体などさまざまなアクターのつなぎ役になれたらと思っています。
久保川さん:私はこのままTransition Asiaで長期的にお仕事をしていきたいなと思っています。意志と能力さえあればあれもこれもとどんどんアサインメントが増えて、自分をどんどん成長させられる極めて上昇志向なコーポレートカルチャーなので、そこが非常にいいなと思っています。給与の面が気になるというお話があったのですが、私の場合はこれまでのところと遜色なく、満足しています。
ただ、脱炭素をめぐる情勢や活動費を出す財団の意向によって今後の方針が決まっていくため、すべてを自分たちの意志だけで決められるわけではありません。そういう意味では、スペシャリストを目指すかジェネラリストを目指すかというキャリアの選択肢は、頭の片隅にはありますね。
キャリアの選択肢に、セクターを超えた転職を
サステナブルコミュニティの山路さん、自然エネルギー財団の平神さん、そしてTransition Asiaの久保川さんのキャリアストーリーはいかがでしたか?気候変動への取り組みをより効果的に、より早く進めていくには、企業・政府・非営利などのセクターを超えて、人財やノウハウが交流し、共創の機会を増やしていくことが鍵になります。あなたの現在のセクターで培ったスキルや経験を、他のセクターで生かせば、新たな取り組みやアプローチが生まれるかもしれません。
Hoopus.と一緒にあなたの力を活かせる仕事を見つけよう
Hoopus.(フーパス)は、サステナビリティや気候変動問題の解決に特化した求人情報プラットフォームです。気候変動問題へ取り組みたいというあなたの想いに寄り添って、団体様とのマッチングをお手伝いさせていただいています。
ぜひこちらからHoopus.に登録してください。すぐに転職を予定していなくても、情報収集中の方のご相談も歓迎しています。


